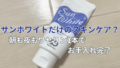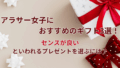先に言うと、万人におすすめできるものではない。が、万人に聴いてほしいものである。
なぜならば、帯域のバランスやそもそもの音の特徴などが他のイヤホンとは異なるためである。もっと言えば、その”偏り”が、最近の”普通”のイヤホンで耳を鳴らしている現代人には違和感として受け取られる可能性がある。
キーワードは、①音が素である、②音に実体感がある、の2つである。この辺りのキーワードが気になる方は是非読んでみてほしい。
先に断ると、このイヤホンは、他のレビューのように、音場についてや帯域ごとに見出しを分けて記事を書くことに意味がないように感じたので、全体的な所感を述べるような形式を採っていることをご承知おきいただきたい。
もちろん、わかりやすい部分として帯域別の量感や質感などについて全く書かないわけではない。
では、レビューである。
RosenkranzというメーカーのRK-Silver/BS(以降BSと言う)というものである。なお、BSはじめ、Rosenkranzのシルバーイヤホンシリーズの一部には、内部配線を別の線材に変更しているVerUPというラインナップもあり、今回のレビュー対象のBSは内部配線VerUP版である。
ちなみにケーブルは、同社のHP-Tinned Flex/2を合わせている。
聴き始めて直後の所感は以下である。
・ボーカルが近い
・低域の量感が多い
ボーカルの近さについては、MH334SRを常用している私の耳でも感じられるポイントだった。ボーカル好きの私としては嬉しいポイントである。
低域の量感について、ここによって好き嫌いが分かれると思った。初めから低域に該当する楽器がないような音源ではただただきれいな音であるが、それがある場合には、一気に低域に支配される世界になる。ボーカルや高域にも若干被りがあり、少なくとも分離能に長けているわけではない。
が、そのまま聴いていると、以下のような所感を覚えた。
・音色や質感に着色がない(限りなく生に近い)
・音に実体感がある
まず、着色がない点である。音の裸、素の音とはこういうものなのかとじわじわと実感させられた。例えばSONYのCD900ST(ヘッドフォン)などは素の音という意味で広く普及し使われているが、あれほどシビアで乾ききった音ではない。むしろあれは、音を乾かすことによって、良く言えば歯切れのよさを出しているように感じられる。
また、普段私が使っているMH334SRやES60は、限りなくニュートラルな音色だと思っていた。
が、BSの後に聴くと、音色はニュートラルではあるが、リスニング用に適度な温かみや湿り気が混じっているように感じられ、その意味では音が裸ではないように感じられた(その2機種はほぼ完全にニュートラルであると思っていたのでその意味では驚いた)。
続いて、音の実体感である。BA機が繊細な表現を得意とする代わりに迫力や実体感に欠け、DD機が迫力を得意とするというイメージはざっくり普及していると思われるが、BSは単に迫力だけで押し切ってくるパワー系ではない。
例えばシンバルの音にしても人の声にしても、迫力はないものの”本当にそこで鳴っている”という粒子を感じられる。それがつまり実体感の正体である。驚くことに、解像度が高すぎるわけでも情報量が多すぎるわけでもないのに、その粒子を感じられるのである。
音が非常に素であること、そしてその音に実体感があることによって、BSは唯一無二の存在になっている。
Bluetoothの規格やドライバーの性能が向上することによって、そこらのミドル機やハイエンド機に近しい音がするワイヤレスイヤホンはちょくちょく登場しているような気がするが(ちなみに、例えばFalcon MaxやCOTSUBU for ASMRなど)、この点については他の追随を許さないばかりか、Rosenkranzだからこその音作りであるように思う。
話を戻すが、音の素性や実体感というのは、特にライブ音源においてわかりやすい。
例えばストリートピアノをiPhoneで録音したような音源では、実際にそこで聴いているような感覚がある。盛った言い方をすれば、デジタル機器を通して聴こえる音と、実際にこの耳で聴く音との間にある壁が取り払われているかのような感覚である。
また少し余談になるが、「生々しい」や「目の前で演奏されているよう」といったレビューを世の中のイヤホンのレビューで見かけることがある。私は、それは2種類に分類できると考えている。
1つは、文字通りの生々しさである。ライブ会場に行ってアーティストの演奏や歌声を実際に聴いている時に覚える感覚である。そしてもう1つはデジタル的な生々しさであり、例えば4Kや8Kの大画面テレビで高精細に解像度高く映像として見ている感覚である。
こちらについては、デジタル音響の進化や、例えばズームした時の肌の質感の表現など視覚から入ってくる情報もあり、生々しいと表現することは可能であると考えている。
話を戻して、BSの生々しさとは、明らかに1つ目の生々しさである。
デジタルデジタルした時代において、音楽を聴く際に、こういう周波数特性の波があるからとか、高域がこうだから低域がどうだからとか、各帯域や定量的すぎる指標で音楽を聴く道具を測ることに対して警鐘を鳴らしてくれた。
もちろん、資金が無限にあるわけではない中、また気軽に試聴にも行けない環境においては、そうした指標は自分が買うかどうかを検討する上で有意義であることは認めるし、実際に音の特徴の一端は掴めると思う。
が、音楽を聴く際、周波数を気にしているだろうか。音楽を聴くとは、純粋に楽しい行為であり、ライブ音源などにおいて、そのときどきのアレンジを楽しんだり、パフォーマンスを通じてアーティストの想いが伝わってきたりと、単に耳に入れるだけのエンターテイメントにはとどまらない。
繰り返し述べてきたように、BSでは、限りなく素に近い音や、その場にいて感じられるものを忠実に表現しているように感じられる。そもそも音楽を聴くとはどのようなことなのか、基本に立ちかえらせてくれる。
解像度がどう、高域がどう、といった分析的なことを考えるようなことだっただろうか。幼い頃に音楽を聴いて鼻歌を口ずさんでいた頃、またライブを楽しんでいるとき、そんなことを考えて音楽を聴いていただろうか。Rosenkranz RK-Silver/BSは、そんな原点を思い出させてくれた。
持っている人も少なく、中古が出ることはほぼなく、新品をいきなり注文するにはハードルが高いものではある。が、何かの折りに巡り合ったときには、ぜひ聴いてみていただきたい。
追伸)同メーカーのさらに上のモデルや、ケーブルを変えることによって、低域の量感といった音のクセはなくすことができる。加えて、音の実体感や自然さが増し、結果として普段私たちが耳で聴いている生音に限りなく近くなるため、この点はいかようにも改善の余地があると思われる。今後上位のモデルを手にしても、この原点を想起させてくれたBSは大切にしたい。